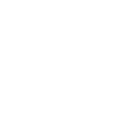トンローのソイ38に佇むピンクの園舎が特徴のメロディー幼稚園。
1981年に設立されて以来これまで多くの園児を送り出してきた。
バンコクの日系幼稚園では最大級の規模を誇る歴史ある日系幼稚園だ。
「私はメロディー幼稚園と共に育ってきました。」と話すのは同園の幼稚園理事長兼園長のウドムマナさん。
ナナ先生の愛称で親しまれる彼女は日本にルーツを持つ母が設立したメロディー幼稚園の1期生。
メロディー幼稚園の成長を1番近くで見届けてきた存在だ。
教育に従事する母の背中を見て、教育者を志したのは必然だったと話す。
タイの高校を卒業後は日本語を習得し早稲田大学に見事合格。
教育学部教育学科で教育心理学を学ぶなか学問の奥深さに魅了された。
米国で発達心理学を学びたいという思いから米国コロンビア大学院教育学科修士課程に進むことを決断。
米国の発達心理学は、人が家庭や学校、地域社会といった環境の中でどのように成長し、学び、心や体の健康を育んでいくのかを研究する学問。
多角的な視点からより良い成長環境を考え、学びを深められる環境に没頭したという。
コロンビア大学院を卒業後は幼児教育への更なる探求とアメリカの幼児教育研究を牽引する教授の下で学びたいとの思いから、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校大学院教育学科博士課程に進むことを決意した。
合格者はわずか3名という厳しい選考基準を見事突破したのだ。
入学後は幼児発達心理学を専攻し、様々な環境や背景を持つ子どもたちがどのように成長するのか研究に打ち込んだ。
タイの幼児教育と米国教育との比較研究やユネスコのインターン生としてアジア太平洋における幼児教育の政策にも関わるなど、未来の教育をより良くするため日々研究に打ち込む日々はやりがいに満ちていたという。
研究者としてキャリアを積み上げていた彼女に転機が訪れる。
2009年、創設者である母が病に倒れタイへの帰国を決意したのだ。
その後母の意志を引き継ぎメロディー幼稚園の経営を担うことになった。
研究者として「より良い環境とは何か」ということを追求してきた彼女にとって現場に立つことは新たな挑戦だったという。
「学問としての教育」と「現場での教育」は決して同じではない。
理論と実践をつなげることがより良い幼児教育につながると確信し改革に取り組んだ。
その中で生み出されたアイディアが「クッキング教室」だった。
園内に子ども専用のクッキングスタジオを併設し、子どもたちが料理を通して学びを深める“食育”に力をいれたのだ。
同園では子どもたちの心と頭だけでなく大事な「体作り」を「食」を通してサポートしている。
子どもたちに提供される給食は日本人栄養士監修の下、化学調味料不使用で塩分濃度をチェックするなどこだわった。
その後、現場で得た学びが研究成果としても活かされることになる。
タイ保育園における栄養・衛生管理のガイドライン作成や執筆活動にも力を入れ、2019年に出版した「食育に関する報告書」は優秀賞を受賞。
現在は、ユニセフタイランドと連携し、タイ企業内保育所の設立支援コンサルタントとしても従事している。
経営においては時代のニーズに応じて、バンコクの日系幼稚園で初めて英語保育をメインにしたインター部の設立。
科学実験などを通して思考力や問題解決能力を育むSTEAM教育の導入や、安全面を配慮し園バスにGPS機能を搭載するなど様々な取り組みを行ってきた。
また、2024年にはソイ49に「メロディーナーサリー」を新設。
メロディーナーサリーはバンコクで利用しやすいナーサリーに特化し、室内で砂遊びや水遊びもできるなどバンコクの気候や生活環境に合わせた設計となっている。
自身も母親である彼女は「育児において最も大切なことはお母さんが幸せであること。これからも子どもたちの笑顔を支え保護者に寄り添う教育者でありたい。」と目を輝かせた。